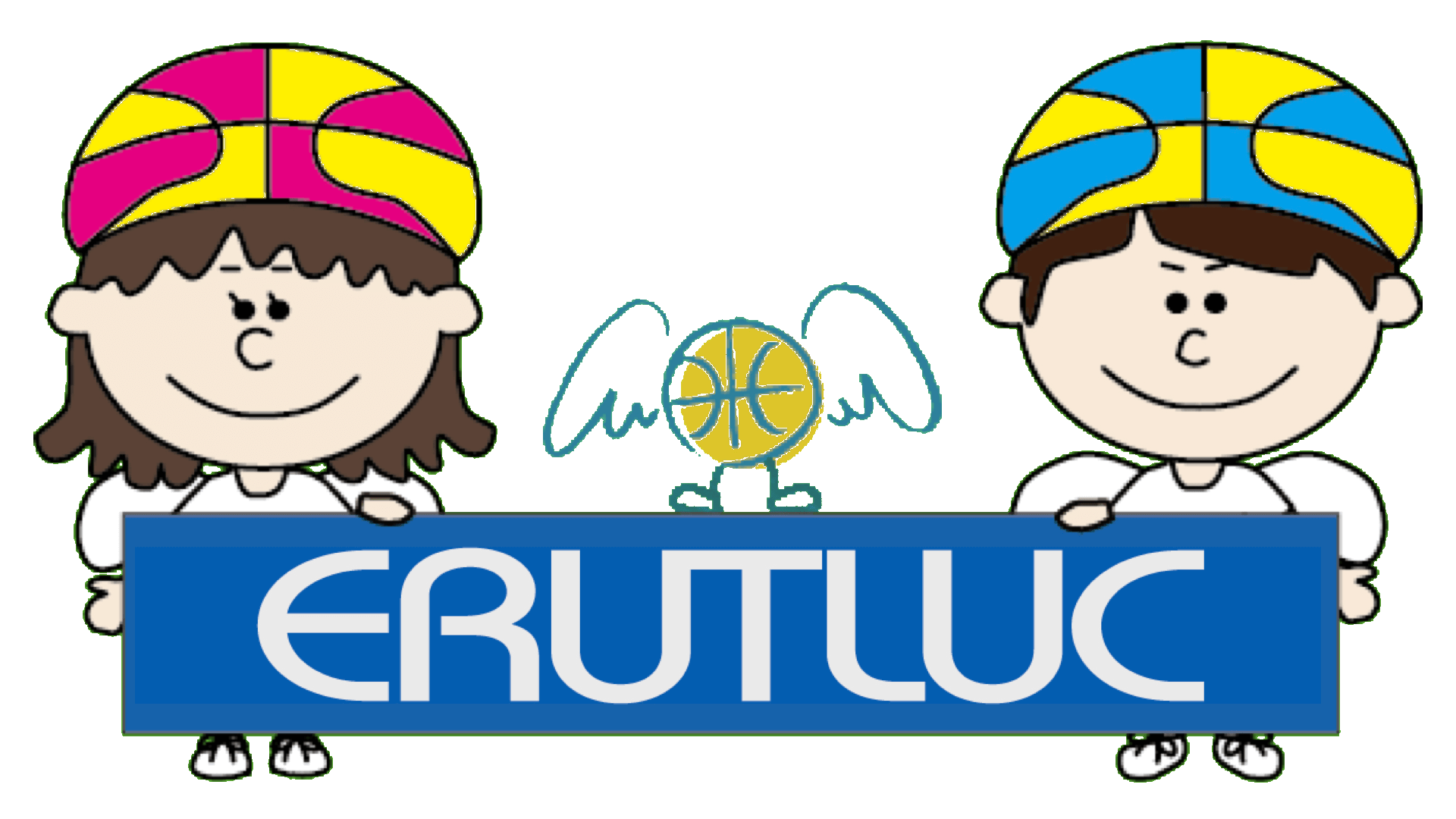【エルトラックが教える】練習計画の立て方
<p>やるべきこと、やりたいことがあまりに多くあります。<br />
練習計画概観
<p><span style="font-size:20px"><strong>■計画とは何か </strong></span><br />
スタイル(目的地)を決める
<p>「何を練習するか=選手に何を伝えるか」<br />
何を練習するかを決める
<p>目指すべき場所が決まりました。次は道のりを決めましょう。<br />
プレー原則の例 「ハーフコートオフェンス」
<p>前述の通り、どのようなスタイルを目指すかによりプレー原則も変わります。<br />
いつ、どれくらい練習するかを決める
<p>さて既にお気づきかもしれませんが、このプレー原則はそのまま「何を練習するか」の答え、つまり練習テーマとなっています。</p>
まとめ
<p>非常に駆け足となりましたが、以上が練習計画についての提案になります。<br />
ERUTLUC(エルトラック)
株式会社ERUTLUC
バスケ 指導ノウハウに関連する記事